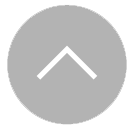【阪急電車おしらべ係 第28回】
正雀車庫に保存されている名車とは?

【2021年9月配信】
読者の皆さんからお寄せいただいた、阪急沿線でふと見つけた「気になるもの」や「面白いもの」などを、阪急沿線おしらべ係のトッコが調査する「おしらべ係」。
今回お送りするのは鉄道ネタです。阪急電車にまつわるこんな質問をいただきました。
「正雀車庫には、一般公開されていない古い名車が保存されていると聞いたことがあります。どんな車両なのでしょうか?」
正雀駅のホームから見える広大な敷地の正雀車庫。駅のホームから見ることができるのはどうやら現役の車両だけのようです。
普段は見ることができない名車とは、どんな姿をしているのでしょうか。早速調べに行ってきました!
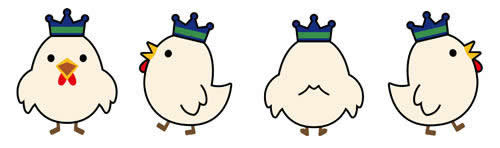
まずは正雀車庫の内部へ

車庫のどこかに保存されている名車を探るべく、正雀車庫の中を特別に取材させてもらうことにしました。
今回ご案内いただいたのは、正雀車庫に勤務されている技術部の草地さんです。子どもの頃から電車が大好きで、今も鉄道模型を集め続けているとのこと。
そんな電車一筋の草地さんの背中を追って広大な正雀車庫の中を進むと、車両のメンテナンスを行っている場所に到着。

そこからさらに奥へと進むと...
「こちらです」

そこには、普段見慣れた阪急電車とは異なる顔立ちをした車両が並んでいました。今にも走り出しそうな凛とした佇まいです。
時代を駆け抜けた個性的な名車たち
正雀車庫に保存されているのは、当時の先端技術を結集して製造され、長年活躍したのちに引退した、かつての名車たち。
時代を駆け抜けた5両の車両が当時の姿に復元され、大切に保存されています。
それでは、正雀車庫の保存車両を製造年の古い順に見ていきましょう。
こちらは1910年に製造された「1形」。

阪急電鉄の前身である箕面有馬電気軌道の開業に合わせて作られた最初の車両です。この時から阪急の伝統色であるマルーン色が使われています。
続いて1925年に製造された車両「10形」。

主に千里線で活躍し、一部は能勢電鉄線にも貸与されました。1966年に引退後、製造当時の姿に復元されて正雀車庫で保存されています。
こちらは、日本で最初の量産全鋼製車両として、1926年に建造された「600形」。

1975年に引退した後、製造元の川崎重工業兵庫工場(旧・川崎造船所)で保存されていましたが、2010年に阪急電鉄開業100周年の記念事業として復元され、現在に至ります。
続いては、1927年~1929年にかけて製造された「100形」。通称P-6(Passenger Car-6)と呼ばれています。

本格的な長距離高速電車の草分けとなった車両で、鉄道ファンの間でも人気があります。
そしてこちらが1930年に製造された「900形」。

「600形」と同じく全鋼製車両ながら、画期的な軽量設計を採用していて、「快速阪急」の象徴ともいえる車両でした。
以上が正雀車庫の保存車両です。
どれも阪急電車の歴史を語るうえで欠かせない名車ばかりです。子どもの頃から鉄道ファンであり、車両技術の専門家である草地さんに、特にお気に入りの車両を聞いてみると...
「個人的には、『P-6』ですね。動態保存されているというのがやはり大きな魅力ではないでしょうか」
動態保存...ということは、今も動くということですね!?「P-6」が製造されたのは約90年前のこと。それが現在も動作するなんてすごいです。
「復元作業を行っていた頃は、幸いにも『P-6』の現役時代を知る技術者がまだ社内にいたんです。当時の技術を教えてくださる大先輩の存在があったからこそ、動態保存を実現することができた。そういう意味でも『P-6』は貴重だと思います」
先輩から後輩へ、脈々と受け継がれてきた技術によって今も生かされている「P-6」。一般には公開されていないその姿を見ることができて感動しました。
「せっかくだから、パンタグラフを上げましょうか?」
側で見ているだけでも満足なのに、通電した状態まで見られるなんて、こんなうれしいことはありません!鉄道ファンの方々にもご覧いただきたいのでぜひお願いします!
ということで、早速運転席へ。

「マスコン、ブレーキという基本の配置は現代と同じですが、まずはパンタグラフを上げるための空気を送り込む必要があります」
パンタグラフを上げるための空気を送るこの装置は、復元に際し製作したものだそうです。

こちらは「手ブレーキ」。運転中には使わず、車両を留め置く際に転動を防止するためのブレーキです。

当時の装置をあれこれ見ているうちに、圧力計が適正な位置に。いよいよ走行できる状態になりました。しかし、今回はこれまで。

車内に視線を移すと、照明のともった客室はレトロで風情があり、瀟洒な雰囲気が漂っています。

「客室の見どころは、白熱球ですね。蛍光灯がなかった時代に、当時の先端技術を駆使し、最新鋭で最高の客室を作ろうという技術者の熱意が伝わってきます」

他にもよく見ると、網棚の意匠や、

手書きされた車番など、当時にタイムスリップした気分が味わえます。

こうして通電した状態を撮影できるのも、日々きちんとメンテナンスを行っているからこそ。動態保存のため、可動部に油を定期的に差す必要があり、作業は1日がかりで行われるそうです。
お客様を乗せて走る現役の車両は言うまでもなく、保存車両も同じように、日々手間をかけて丁寧にメンテナンスが行われているんですね。
まとめ
正雀車庫に保存されている名車の調査をきっかけに、動態保存の「P-6」が動く様子や、大切に受け継がれてきた技術について知ることができた今回。
普段乗っている阪急電車を観察し、どのような発展を遂げてきたのか改めて調べなおしてみると、また新たな発見に出会えるかもしれませんね。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございます。阪急沿線おしらべ係では、阪急電鉄だけでなく、阪急沿線アプリで連携しているグループ会社(能勢電鉄、阪急バス、阪急タクシー)に対する質問も受け付けています。
みなさんも気になるものや知りたいことが見つかった時は、ぜひ「阪急沿線おしらべ係」まで質問をお寄せください。